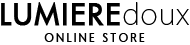☆物語から始まるFruje(フルージュ)はフルーツをモチーフとしたジュエリーブランド。
【最近届いた読者の声】
★★★★★ 決意を固める場面はとても感動的です
これは素晴らしい物語ですね!ワンディの成長、夢の追求、そして親友や母との関係が描かれていて、感情が深く伝わってきます。特に、「想像のおもちゃ箱」や... 続きを表示
★★★★★ 心に残るメッセージが込められている
『不思議な木のフルージュ』の物語は、魔法のような木とその果実を巡る冒険と成長の物語ですね。物語の初めは、フルージュという神秘的な木が果実を通じて... 続きを表示

【はじめに】こちらのブランドはエイプリルフールを記念してご紹介しています。そのため、ブランドの存在はもちろん商品の入荷もございません。悪しからずご了承くださいませ。また、”不思議な木のフルージュ”については店長の創作活動の場として描いており、物語の完成を目指し進めております。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
- 第2章 想像のおもちゃ箱
- 第3章 ダニエル・ウィンストン
- 第4章 庭小屋の宝石屋
- 第5章 幸運を呼び込む訪問者
- 第6章 虹のダイヤと工房の職人たち
- 第7章 ジュエリー・デザイナーズ・コンテスト
- 第8章 聖夜の再会
Fruje(フルージュ)
- < Prev
- Next >
全4商品 1-4表示
-

 frujoux(フルージュ) ゴールド Newtone ニュートン ピアス
SOLD OUT
frujoux(フルージュ) ゴールド Newtone ニュートン ピアス
SOLD OUT
-

 frujoux(フルージュ) ゴールド Strawberry Calyx イチゴのヘタを被った一粒ネックレス
SOLD OUT
frujoux(フルージュ) ゴールド Strawberry Calyx イチゴのヘタを被った一粒ネックレス
SOLD OUT
-

 frujoux(フルージュ) ゴールド Banana バナナ ネックレス
SOLD OUT
frujoux(フルージュ) ゴールド Banana バナナ ネックレス
SOLD OUT
-

 frujoux(フルージュ) ゴールド Fruits Smoothee フルーツスムージー ピアス
SOLD OUT
frujoux(フルージュ) ゴールド Fruits Smoothee フルーツスムージー ピアス
SOLD OUT
全4商品 1-4表示
- < Prev
- Next >

不思議な木のフルージュ
【あらすじ】
舞台は1930年代のイギリス。ある森に存在するフルージュと呼ばれるその木は世の中すべての果実を実らせる不思議な木。果実を食べれば願いが叶うと噂の不思議な木。偉大な科学者アイザック・ニュートンの母校に通う、15歳のワンディは大きなイチゴを食べ、3つの願いをする。帰り道に偶然であった女の子に恋をし、再会するため宝石屋をはじめるところから物語は進んでいく。
第1章 大きなイチゴと黒いリンゴ
むかし、むかし、あるところにとっても仲の良い夫婦がいました。夫は、絵を描くのが大好きな妻のために、 いつも新しい道具を贈っていました。妻は、果物が大好きな夫のために、いつも食卓にたくさんの果物をそろえていました。
ある日のこと、木いちごが食べたいと言っていた夫のために、妻のジュリエットは森へと出かけましたが木いちごはまったく見当たりません。 どうしても食べさせてあげたいと思っていたジュリエットは、しかたなく森の奥へ奥へと探し歩いていきました。
すると、光輝く大きな木に出会います。なんとその木はリンゴや、マンゴー、桃などありとあらゆる果物が1本の木から実っているのです。 さらに足元を見渡すと探していた木いちごがそこかしこに実っていました。
ジュリエットはその美しい木をしばらくうっとりと見つめていました。「あーーなんて美しくて魅力的な木なのかしら」、「この木は・・・」、 「喜びのフルーツ・・いや、違うわ・・」「ふしぎな木の・・・フルージュ」「そう、不思議な木のフルージュがぴったりだわ。」
ジュリエットは楽しそうにその木と会話をしながら、木いちごやたくさんの果物をカゴいっぱいにつめて、家へと持ち帰りました。 その夜はテーブルいっぱいの果物が食卓を飾り、夫もお目当ての木いちごをたくさん食べることができて、とても喜んでいました。
それからしばらくして、ジュリエットはお皿やカップに果物の絵を描いた、手作りの陶器を家事の合間に作っていました。 その陶器は人から人へと人気が広まっていきました。気がついたときには”ジュリエット・ストーリー”という彼女の名前で、 この国一番の陶器メーカーになっていました。
あっという間に大成功を収めたジュリエット、成功の秘訣は?と聞かれて、不思議な木のフルージュに出会った時の話をしました。 それを聞いた町の人たちは、その木に実る果実を食べれば何でも願いが叶うと噂をし、多くの人たちがフルージュへと足を運ぶようになりました。
裕福な生活を手に入れたジュリエットは、ひとりの女の子にも恵まれ、いつまでも家族仲良く幸せに暮らしましたとさ。・・・おしまい。
-----イギリス発の陶器メーカー、ジュリエット・ストーリー誕生秘話より-----
ジュリエット・ストーリーが誕生したのは今から100年以上も前のこと、すでに彼女はこの世にいないが情熱を捧げてきた作品たちは 次の経営者に受け継がれ、イギリス中の人たちから愛され続けている。イギリスの家庭には必ずといっていいほど彼女の食器が見られるだろう。
そして、不思議な木のフルージュは僕たちの町グランサムから北に30マイルほど行った、シャーウッドの森の中にある。 むかしは果物がよく実っていたというが最近はひとつの果物すら見ることもなく、行く人も年々少なくなっている。 それでも、女子たちの間では”ジュリエット・ストーリー”は憧れの存在であり、たびたび話題になっていた。
「あーーーー本当に素敵な話だわ。ねえ、そお思わない」「ほんと、ジュリエットがうらやましいわ」ほら、今日も学校の女の子たちは両手を握りしめて神に祈りをささげているみたいにその話で盛り上がっている。 「あーーーーうるさい、うるさい、うるさい、そんな話、大人の作り話のウソに決まっているさ!そう思うだろワンディ」僕と同じ15歳で幼馴染のフレディ・エルガーは女の子たちの会話に心からうんざりしていた。 「あーーーーわかんない、でもおばあちゃんもときどきその話をしてる」僕、ワンディ・ウッドのおばあちゃんもジュリエットの物語は大好きだ。
「そんな話が本当だったらみんな大金持ちじゃん。・・・なあワンディ、明日からの休みにフルージュへ行ってみないか。」フレディのこのひと言を聞いた時、何かに引き寄せられる気がした。 「そのなんだ、俺たちが何でも願いが叶うという果実を見つけてだな、その話がウソだってことを証明してみようぜ。そしたら俺たち人気者になるだろう?」 「そうだね、おもしろそうだし行ってみようか」 ・・・・・
こうして、不思議な木のフルージュを目指し、ワンディとフレディの冒険は始まった。
翌朝まだ夜が明ける前、町外れにある石碑の前でふたりは待ち合わせをしていた。「よお、きたな」先に待っていたフレディはワンディの肩をたたくと、森へとつづく道を走りはじめた。ワンディも「よしっ」と追いかけるように駈けていった。
ハアッ、ハアッ・・・もう、走り始めて3時間は過ぎただろう。フレディが息をきらしながら、ちょっと休憩しようとワンディに声をかける。森へと続く1本道、そばにある大きな石に腰掛た。持ってきた水をピシャっと顔にかけたあと、ゴクりゴクりとふたりはのどの音を大きく響かせた。汗もひいて、さあ進もうかと思ったとき、ひとりのおじいさんがこちらに向かって歩いてくるのが見えた。ふたりは行こうかと思ったが、そのおじいさんのことが気になり、通り過ぎるのをまとうかと目を合わせて合図した。
「君たちはフルージュに向かっているのかい?」おじいさんが話しかけてきた。 「そうさ。おじいさんも知ってるんでしょ、不思議な木のこと。」聞き返すワンディ。 「ああ知っているとも、私もあの木のおかげで今があると思っている、たったいま感謝を伝えてきたところだ。」 少しイラついた感じでフレディは言い返す。「ウソなんでしょ、願いが叶うとか」
おじいさんはひと呼吸おいて「ああ、町の多くの人も果実を口にしては、あの木の話はウソだと言っておった。」 「やっぱり、そうなんだ!」フレディは満足げな表情を見せた。腑に落ちない表情をしているワンディ「おじいさんはさっき、あの木のおかげっていったけど、本当はどう思っているの?」 おじいさんは、たっぷりの目じりのシワを見せながら笑みを浮かべた。 「ありがとう聞いてくれて・・・。私は感謝をしてるんだ。フルージュに。それがわたしの答えだ。」
フレディはまだ何か言いたそうだったが、おじいさんはスッと少年たちに背を向け、左手でゆっくり手を振りながら町のほうへと歩きだした。少しのあいだ、うしろ姿を見ていたフレディは、まあいいやと言わんばかりにワンディの手をつかみ、森へと続く道をゆっくりと走りはじめた・・・。
ふたりはただひたすらに走り続けていた。ようやく、シャーウッドの森の中に入ってからも、いくつかの分かれ道があり迷うこともあったが、こっちの道だといわんばかりに道脇の木に目印がある。それはバナナの皮が干からびたようなものでつくってあった。ふたりで言い合いにもなったが、ワンディの意味があるに違いないと言う言葉に、フレディもしぶしぶ道を進めていく、するとあきらかに大きくひらけている出口が遠い先に見えてきた。
「おい、あそこじゃないか!」フレディは久しぶりに大きい声でさけんだ。「きっと、そうだろう。」ワンディも全身が汗まみれになるほど疲れていたが、ふりしぼる力でさらに足早に走っていく。その場所へ、ふたりが到着する。「まぶしいっ!」ふたりとも同時にさけんだ。そのまぶしさであたりの景色が真っ白になったが、目が慣れてきたのかようやくその中央にある大きな木の存在に気づいた。
「おお、これだこれだ。これがフルージュってやつだな。」フレディはその木をなでるようにさわりながら口にした。「こんなに大きい木なんだ。学校の校舎よりも高いんじゃないか。」口をポカーンとしながら木の上のほうを見ているワンディ。さっそくふたりは果実を探し始めることにした。木のまわりをぐるぐると見渡し歩きながら、”お〜い見つけたか〜””ないけど、そっちはどうだ”と声をかけあう。しかし、いっこうに見つかる気配はない。
しびれをきらしたフレディ「チェっ なんだよ、せっかくきたのに果実がないって。オレたちツイてねーな。」ワンディも同じことを考えていたが、木から少しはなれたところにある立て看板に気づく。近づいてみると立て看板にはこう書いてあった。
”果実を実らせるには願いをこめたお水が必要である。”
”果実はいつ実るかは誰にもわからない”
遅れてその看板に気づいたフレディもその言葉を見つめながら「願いをこめたお水って、そこに流れている川の水のことじゃないか」 木から町を見渡すほうに目をやると、小川が流れていることにワンディもうなづいた。小川のそばまでいくと、水を運ぶ桶が無数にあることが目に留まり、たくさんの人がきてるんだと感じたワンディ。ふたりはその桶で出来るだけいっぱいの水を汲み、もう一度木の前に立った。
「これが願いの水ってことであってるのかな?」ワンディはフレディに聞くと「たぶんね。」そういいながら、木の根元へ水をかけるフレディ。「ふ〜ん。」ワンディもつづけて水をかけた。5分ほど何か起きるのかなと身構えながら、耳をすませ、上目づかいで果実が急に現れるのではないかとキョロキョロとするふたり。
「あ〜つかれた!やっぱり、ダメじゃん。」そういいながらフレディは、木にもたれるように座り込んだ。ワンディも、ちょうどフレディとは真反対に座り込む。がっかりしたふたりに急に眠気がきたようだ、こくりこくりとふたりは寝てしまった。・・・・・
最初に目が覚めたのは、フレディのほうだった。どれくらい寝ていたのだろうか?かなり長い時間寝ていたのは間違いない。立ち上がり、大きく背伸びをしようとしたとき、茂みの中にある何か、黒いものに気づいた。
少しかき分けて、その黒いものを見た瞬間、「ええっ!あったぞ。あったぞ。」と大声で叫んだ。その声にびっくりした、ワンディも目を覚す。「ワンディ、見てみろこれリンゴだろ!」
目をこすりながら、ワンディもたしかに、リンゴかなと思った。「フレディ、リンゴのようだけど、なにか色が悪くないかい」「バカっ!これが何でも願いが叶うという、実っていうことだろ。なんかそんな雰囲気じゃん。」興奮気味にフレディは、その黒いリンゴを大事そうに見つめていた。
「お前は見つけたか?ま・ほ・う・の・み」興奮がおさまらないフレディ。ワンディはあたりを見渡した。「何だよ、魔法の実って。まあ、オレはまだだね。」 フレディはにんまりとした顔で「じゃあオレはさっそく、この実がウソであることを証明するために、家に帰るけどおまえは?」・・・。ワンディしばらくだまる。「オレ、もう少し待ってみようかな。」
「そうか、そうか、ならオレは一足先に帰るよ。証明しないといけないしな。」ぜんぜん、うれしさを隠しきれていないフレディは、 何回もこちらを見ては手を振り、上機嫌で来た道のほうへと向かっていった。・・・・・
フレディが去ったあと、この木のことを考えていた。もし果実を食べて、何でも願いが叶うということが本当だったら、ふと、おじいさんの笑顔を思い出した。あの笑顔はとてもウソをついているようには感じなかった。そんなことを考えていたら、どうしてもその魔法の実が欲しくなった。
あたりがゆっくりと暗くなっていく。看板にも書いてある”いつ実るかは誰にもわからない”という言葉が、心に問いかけてくる、このまま実らないのでは?不安がつのりながらも、もう少しだけまってみようと思うワンディ。朝から何も食べていなかったが、ふしぎとおなかは減っていなかった。
ピーチュピチュピ、ピーチュピチュピ。
ワンディの肩や腰あたりに、6羽のツバメたちがとまって、もう朝だよと知らせてくれている。どうやら、木の下で考え事をしたまま夜が明けてしまったようだ。疲れはぜんぜんないなと確認し、もしかしたら、実がなっているのではと探してみるも、やっぱり見つからない。
ならば今日はどうするか?いくつかの案が浮かんだ。まずお水は、昨日よりも多く朝と、昼と、夕の3回やってみよう。願いを込めたお水ということだから、願いを言いながらお水をかけてもいいだろう。昨日は気づかなかったが、木の周りの雑草が伸び放題だから、空き時間にはこの雑草を取ってきれいにしてみよう。
なんだろう、考えてやっていることがとても楽しく感じていた。最初は、果実のことが気になってしょうがなかったが、そんなことより、この場所へくる人たちがイヤな気持ちにならないように、散らばっていた小川の桶を片付けてみたり、ここへくるときに迷った別れ道の目印に、枯れ木を使って”フルージュへはこの道”と付け加えたりもした。
他は、何かできないだろうかと考えていたら、2日目はあっというまに過ぎていった。さすがにお昼すぎたあたりから、おなかが減っているのは知っていたし、ここまで丸二日何も食べていない。「お腹へったな〜。フレディはあのリンゴもう食べたのかな?」「明日の朝、果実がならなかったらもう帰ろうかな」「今日はとても月がきれいだ」そんなことを考えながら、2日目は過ぎていった。
ザザッーー ブォーー ゴロゴロ ブォーー ザザッーー
すぐにヤバいと感じた――3日目、目が覚めたのはまだ真っ暗の中、大雨だ。しかも、風が異様に強く、とても帰れそうにない。お腹が減りすぎていて、元気もない中、なんとか嵐がおさまるまで待つしかないようだ。出来るだけ風を受けまいと、めいっぱいフルージュの木に身を寄せ、雨風をしのいでいた。「なんか、クラクラする・・。」これまでの疲れと空腹がピークに達し、意識がもうろうとしてきたワンディは気を失なってしまう。そのあとの記憶は、目が覚めるまでなかった。・・・・・
おそらく目が覚めたのは、4日目だと思う。嵐は過ぎ去っていて、まぶしい日差しは体に温もりを与えていた。しかし、体を動かそうにも力がでない。横たわったまま目をこすっていると何やら甘酸っぱく、とてもいい香りが全身を包み込んだ。何の香りなのか?すぐに気になって目を開き、真上を見ると、目に留まったのは大きくて真っ赤な果実だ。「えっ、果実!」
さっきまで、まったく動けなかった体はうそのように動き、それから手の届く位置にあったその果実に触れた。「これ、イチゴだよな」どう見ても、スイカほどの大きさである。いやそんなことはどうでもよかった。すぐにその果実をもぎ取り、口いっぱいにほうばった。「うまい、うまい、・・・。」涙が自然とこぼれていた。
食べきるまでに、そんなに時間は掛からなかった。「こんなに甘くておいしいイチゴは初めてだ」そんなことを言いながら、体じゅうに力がみなぎるのを感じていた。食べきったイチゴは、大きなヘタだけが残った。
力を取り戻したワンディは家に帰ろうとしたが、嵐で飛び散っていた桶が目にとまり、片付けようと小川へ近づいていく、すると小川の中でキラキラと光るものを見つける。その光るものを拾ってみると、宝石のように輝いている石だった。「とても、きれいだ」ワンディはその石をポケットに入れ、帰るべく森を出はじめた。
帰る途中に、ひとりの女の子と出会う。女の子は手を後ろに組み、森の道を右から左へ行ったりきたりと歩いている。少し近づくと顔つきは緊張してこわばりながらも何かの期待に満ちているようで、ゆれる金色の髪は木漏れ日の光で神々しく輝やいている。さらに近づくとあごはとがっていて凛々しく、唇は何とも愛らしく、品を感じさせる鼻、大きい瞳は生き生きとして近づくワンディをずっと見つめている。女の子は道の真ん中でピタリと止まって、ようやく会えたと言わんばかりに極上の笑みを浮かべた。
「あなた、ワンディでしょ?」独特の澄んだ可愛らしい声だった。「顔はわたしのタイプだわ。・・・わたし、この日をずっと待っていたの、もうあれからどれくらいたったかわからないし。とても、退屈だったわ。でも、この日が本当にくるなんて信じられないの。・・・えっ、まって、頭にかぶっているのは何?・・・流行の帽子なの?」女の子はクスっクスっと笑い始めた。
頭の上に大きなイチゴのヘタをかぶっているワンディは女の子に見とれて、ぼーっと立っていた。あまりの可愛さに心を黄金の矢で射られてしまったようだ。ふと我にかえって、イチゴのヘタを帽子がわりにしたことを話そうした。「あっ、いやこれはさ・・・。」話し始めようとしたその時、突然ビュンッと音を立てて突風が吹いた。
かぶっていたイチゴのヘタは飛ばされ、高く舞い上がった。ふたりとも空を見上げ、落ちてくるイチゴのヘタを眺めている。イチゴのヘタはゆらゆらと揺れながら、下へ下へと降りてきた。最後にくるんと1回転して女の子の頭の上に見事に着地した。ふたりは顔を見合わせて笑った。しばらくの間、笑いが止まらなかった。
「ごめんなさい。ワンディの帽子、わたしに飛んできたみたい」女の子はイチゴのヘタを手に取りワンディへ返した。その時、女の子は右手の異変に気づき、素早くその手を後ろへ隠した。もう時間なのねと残念な表情を浮かべながら、ワンディに「またね」と小さく、つぶやいた。それから、女の子は「ワンディはここよ〜っ!」と遠くに見えてくる、大人たちに向かって手を上げ知らせていた。
うしろを振り向くと、そこには何日も帰ってこなかったワンディを心配して、町の人たちが探しにきてくれていた。トーマスさんやメアリーおばさん、隣人のテディおじさんまで・・・その中には僕の母さんもいて「バカっ」といいつつ強く抱きしめてくれた。そうだ、名前を聞いていなかったと思い、あたりを見渡したがもう女の子はどこにもいなかった。・・・・・
そんなわけで、僕は無事に家に帰ることができたんだ。そのあと、どうなったかというと、まず、すぐに帰ったフレディは、持ち帰った黒いリンゴを食べようと切ってみたら、中がひどいほどに腐っていて、とてもじゃないけど食べられなかったみたい。
だから今でも言ってるよ「あの木の話はウソだってね。」母さんから、僕が帰ってこないから、行き先を聞かれたみたいだけど「わからないっ」て言ったそうだ。おいおい。
僕はあの大きなイチゴを食べた日、3つのお願いをしていたんだ。
【ワンディが不思議な木のフルージュに込めた3つのお願い】
1つめ 大きくなったら人を喜ばせる仕事ができますように
2つめ 母さんが幸せになりますように
3つめ みんなが笑顔でありますように
果実を食べたことは誰にも言っていない。日もあまり経っていないし、本当なのか、ウソなのかは、まだわからない。でも、イチゴのヘタと宝石のような石をながめていたときに、ひとつのアイデアが浮かんだんだ。
宝石にイチゴのヘタをかぶせたら、あの子がまた笑ってくれるんじゃないかなって。「あのときの笑顔がとってもキュートだったんだ」こんな気持ちははじめてさ。だから、僕は町一番の宝石屋になると決めたんだ。 今、その勉強をしてるよ。もしかしたら、1つ目にお願いした『大きくなったら人を喜ばせる仕事ができますように』って、このことなのかもしれない。
あと母さんに、フルージュへ向かうときに出会ったおじいさんの話をしたら、「その人はもしかしたらニュートンさんかもねって」言ってた。僕も思わず「あっ、そうだったね」って笑った。僕らの町では相手の名前を忘れてしまったときによく言うんだ。そうしたら、相手を傷つけずに場がなごむだろう。アイザック・ニュートンさんはずっとむかしに僕らの町の学校に通っていた偉大な科学者なんだ。
そうそう、最後に聞いてくれるかい。 お店の名前は”フルージュ”にしようと思うんだ。だって、フルーツとジュエリーを足したらフルージュになるだろう、ほら、あの木と同じ名前さ。
>>第2章 想像のおもちゃ箱